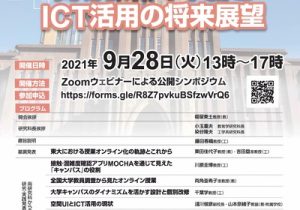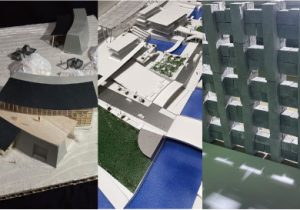2024年度 卒業制作

辰野賞
平井 英佑
まちの遺伝子 壁転写する木密防災
「三大学合同講評会」池田靖史賞&オーディエンス賞 受賞!!
「第34回東京都学生卒業設計コンクール2025」日本建築家協会関東甲信越支部 銅賞受賞!!
「JIA全国学生卒業設計コンクール2025」銀賞受賞!!

中村達太郎賞
ウォルシュ 冠 コルンバ
Porous Jungle 打設と組積の間のMicro climate
Aコース奨励作同時受賞!
「三大学合同講評会」藤村龍至賞 受賞!!
「第34回東京都学生卒業設計コンクール2025」日本建築家協会関東甲信越支部 奨励賞!!

奨励作
Aコース(設計)
坂本 遥 SUKIMANIA
「三大学合同講評会」出展
「第48回 学生設計優秀作品展」レモン画翆 出展
鈴木 陽介 東京イドロジー
「卒業制作2025」近代建築社 出展
須永 数正 新・銀座式開発
中川 功大 多摩川、残コン、ハプニング、
「全国大学・高専卒業設計展示会」日本建築学会 出展
「日比谷ランドスケープデザイン展2025」JLAU講評会 優秀賞受賞!!
堀 智洋 過渡する都市の三面鏡
「日比谷ランドスケープデザイン展2025」出展
ウォルシュ 冠 コルンバ Porous Jungle 打設と組積の間のMicro climate
Bコース(研究)
河原 匠汰 超軽量展開構造物の提案 Tailed fold
丸本 将也 空間ダイナミクスの行く先は…
選評
2024年度の卒業制作は大別すると、オーソドックスなテーマに取り組み完成度を高めた作品と、新たな課題を提起し挑戦したものの成果物としての表現が追いついていないものとの二つに分かれ、初見ではやや物足りなさも感じられた。しかしながら、個々の作品を具に読み解くと、前者においては、既存の問題に真摯に向き合う中で作品に注いだエネルギーや思考の総量には感銘を与えるものがあり、また、後者の中には、学内講評会に選出されなかった作品も含めて、示唆に富む問いを投げかけるものも少なくなかった。また、ランドスケープからエンジニアリングまで幅広い分野を横断して提案がなされたこともこの学年の一つの特徴であり、結果的にAコースの奨励作の中にBコースで提出された作品も含まれることとなった。幅広いテーマを発見したことは学年の共有の財産であり、継続的な議論が望まれるが、それと同時に、テーマの差別化だけではなく、なぜこの場所にこの建築が必要なのかという普遍的な問いに対する理論的な強度も高めて欲しい。
Aコース(設計)
平井 英佑「まちの遺伝子 壁転写する木密防災」《辰野賞》
荒川区の三河島駅周辺に位置する未接道住宅が集中した街区を対象に、木密地域の課題である防火・耐震対策として、既存建物の外部にまちのテクスチャーが転写されるようにRC壁をたてていく。その後、既存建物の解体が進むにつれて、残されたRC壁にスラブと屋根をかけて内部化し、新しい住宅および住環境を提案した作品である。木密地域というテーマは卒業制作で多く用いられたものの、外部を転写していくことによって、これまでには見られなかった独特な形の建物を提案するというコンセプトの面白さ、デザインの高い完成度、一般的な設計による空間とは異なる密度感の魅力が高く評価された。
坂本 遥「SUKIMANIA」〈奨励作〉
中野通りと中野サンモール商店街に挟まれた街区の路地に鉄骨ユニットとグレーチングによるフレームを挿入し、サブカルチャーを好むマニア達が表現、交流、滞留できるミュージアムとした提案である。再開発からあふれた街区の構造を読み解き、中野ブロードウェイに充満するアクティビティを路地へ立体的に浸透させるプログラムは優れており、綿密なリサーチに基づく現代都市への批評として説得力がある。また、都市の隙間を立体化する提案は汎化性を有しつつ、軽快なフレームで実現される空間そのものが魅力的である。他方で、本ミュージアムはマニア達が主体となりつつも広く社会へ開かれており、周辺への波及効果も期待される。計画の外貌となる表通りのアプローチの設計や、路地内部の細やかな建築計画から人びとの滞留や混淆の様子が具体的に示されていれば、より提案の迫力は増したであろう。
鈴木 陽介「東京イドロジー」〈奨励作〉
北品川を敷地に定め、点在する浅井戸の上に塔を建設し、空気と水の循環を顕在化させることで、木密都市のなかに豊かな生活の情景を描き出す提案。私有地の井戸に、地下水の観測所としての役割を見出すことで、都市の水資源に意識を向けさせると同時に、日常の生活の場として、また防災機能を有するインフラとして活用するという着想は、卒業論文から継続する本人の研究が設計として結実したものであり、高い評価につながった。面的な広がりの中で、水を活かした空間の使われ方やそれに呼応する建築の形態についても、地域性を反映したバリエーションを示すことができれば、なお提案が魅力的に浮かび上がるであろう。
須永 数正「新・銀座式開発」〈奨励作〉
銀座の都市組織を温存しながら高層化と容積の大規模化を実現しうる再開発手法の提案である。地域独自のルールに基づきスカイラインを維持してきた銀座だが、近年は都市再生特別措置法の適用による超高層、あるいは巨大なボリュームによる開発の圧力が高まる。本提案は、銀座らしい中小のビル群にメガストラクチャーのチューブを挿入することによって、街区全体を高度に活用して床面積の確保しながら、ビルと路地が織りなす都市組織に親和し、かつ多様な空間を創り出す可能性を示した。既存の都市構造と大規模な都市再開発を揚棄することで新しい銀座の将来像を提案したことが評価される。他方で、本提案と銀座界隈の関係や、大規模な商業空間の将来性については疑問が呈された。この手法が有効に機能する敷地やプログラムが選定されていれば、より豊かな議論を生んだであろう。
中川 功大「多摩川、残コン、ハプニング、」〈奨励作〉
建設現場で余った生コン(残コン)からつくったブロック用い、それを集積することによって創出される川辺の公共空間を提案した。敷地は田園調布の南端、多摩川の水衝部である。残コンという、これまで廃棄物と見なされていた余剰物を活用することで、地域のコミュニティをつなげる空間を提供し、環境にも貢献できる提案である点が高く評価された。一方で、残コンブロックを集積するデザインプロセスをより精緻に提案した方が良かったのではないかという指摘もあった。
堀 智洋「過渡する都市の三面鏡」〈奨励作〉
上野駅前から不忍池にかけて、南北に伸びる要素によって断片的に知覚される都市のイメージを、東西方向に伸びるサンクンガーデンによって再編集し、連続的に結びつけ、無数の群衆の営みを風景に昇華させることで上野に新たな顔を与えようとする意欲的な提案である。操作の手法は、水盤や列植された樹木など伝統的なものであるが、既存の複雑化した交通インフラと相まって、駅前に広がる新たな公共空間の可能性を示唆している。照度変化に伴う夜間景観など、都市の現象と人間の知覚に着目する視点の鋭さに対して、立ち現れる実空間の素材や体験の表現がやや追いついていない点が悔やまれる。
Bコース(研究)
ウォルシュ 冠 コルンバ「Porous Jungle 打設と組積の間のMicro climate」《中村達太郎賞》
ポーラスコンクリートが多孔で水分との相互作用が大きい材料特性に着目し、これまでの舗装用材料という適用範囲を逸脱し、構造材料としての利用を指向した試みで、形状・構法・材料を踏まえ、建築の内部と外部を考慮してまとめた点が高く評価された。
河原 匠汰「超軽量展開構造物の提案 Tailed fold」〈奨励作〉
薄膜を張った極細骨組が自由多面体に展開する構造デザインを提案し実作しています。骨組を頂点毎に異なる角度の変化率で展開させるために古代のアンティキテラ島の歯車のように見える接合具も開発して3Dプリントしてみせており、これらの成果が高く評価された。
丸本 将也「空間ダイナミクスの行く先は…」〈奨励作〉
本作品は、建築と情報をつなぐセマンティックデータモデル(SDM)を空間・人・環境のダイナミクスに活用するという先端的課題に対して、具体的な形に表れにくいデータ駆動のフレームワークを模型で実際に提示しています。SDMの環境・設備制御や空間利用への応用可能性をインタラクティブに体験できる意欲作であることが高く評価された。
作品リスト 51名
Aコース(設計) 37名
松本 竜弥 木と八幡宮の式年造替 「日比谷ランドスケープデザイン展2025」出展
物袋 正雄 高田馬場駅前再開発
坂本 遥 SUKIMANIA 奨励作
浅井 夏海 温暖化のなかで暮らす、エネルギーを知る
有賀 桃花 まる・サンカク・四角 ~多様なニーズに応える救護施設と地域社会のつながり
石田 琴音 誰もがありのままに生きる、を当たり前に〜障害や年齢を超えた地域共生のあり方〜
井上 皓陽 都市水産業を考える
上本 詩織 まちぎわのperch
大沼 吾朗 破局の前に 想像的遺構のすすめ
大山 賢三 広告する建築
沖 直弥 新・神楽坂見番
越智 充有 最終処分場の30年
越智 悠斗 しみこむ緑、ほどける街 ~自然と都市の新接点~
加藤 新大 小石川の図書館
加藤 拓真 Egg 〜3Dプリンターで建てる二世帯住宅〜
木下 蒼平 学びの丘
木村 凌 0m地帯の砦
木村 留実 にしおぎコンプレックス
小板橋 りさ トランスナショナル散歩道
小暮 裕乃 空中風呂 高層マンションの新しい在り方
杉浦 英怜奈 東京漂流
鈴木 日向 軌道分庁 駅と電車がつなぐ、新しい三島市役所のカタチ
鈴木 陽介 東京イドロジー 奨励作
須永 数正 新・銀座式開発 奨励作
冨田 玲子 まちの止まり木 —商店街沿い既存建築群における、境界のほどき方の提案
中川 功大 多摩川、残コン、ハプニング、 奨励作
西垣 昂揮 炭鉱、廃墟、そして
能勢 豊樹 墓地に線を引く
萩原 歩香 地下から地上へー路面電車がつくる歩行空間
平井 英佑 まちの遺伝子 壁転写する木密防災 辰野賞
平石 充 水上に佇む学び、憩い、味わいのステーション
福本 征悟 駅舎の記憶、未来のかたち
堀 智洋 過渡する都市の三面鏡 奨励作
松浦 有哉 廃材拠点 ~解体と再構成による空間の産出
森 貴裕 0-19
森部 碧 湧水と共に住まう「はけ」の生産緑地 「日比谷ランドスケープデザイン展2025」出展
劉 湛辰 陽光さしこむ駅間
Bコース(研究)14名
鈴木 徹志 ベッドを利⽤した寝室内低周波騒⾳低減の試み
大和田 直人 RC造腰壁・垂れ壁付柱の剛性評価について
藤間 朋久 Modular Air Conditioning –空調設備の可変–
ウォルシュ 冠 コルンバ
Porous Jungle 打設と組積の間のMicro climate 中村達太郎賞・奨励作(Aコース)
太田 創 増上寺・芝公園の文化的価値の考察
川上 悠輔 ノルウェー木造軸組教会の構造に関する研究
河原 匠汰 超軽量展開構造物の提案 Tailed fold 奨励作
末松 寛喜 令和6年能登半島地震被災地における木造住宅の耐震補強〜土蔵に着目して〜
長岡 佑亮 シラバス情報を活用した大規模言語モデルによる空調・空間最適化のための出席人数予測と時間割生成
福田 孝樹 狭隘道路に関する試行的提案 デジタルツインと「外構ロボット」によるシステム構築
福地 竜紀 空間充填の構成とボキャブラリー
丸本 将也 空間ダイナミクスの行く先は… 奨励作
和多 毅 片側袖壁付柱の破壊形式
山室 彬紗 実態調査に基づいた既存在来木造住宅の耐震改修手法の提案